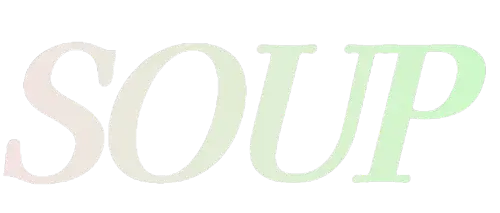Q.「演奏面」のご自身の変化は?
思い切って弾く、楽しんで弾く、ということを何より学べました。誰かと合わせて弾くためのテンポや合図についても大きな学びがありました。
曲に対する解釈がより深まり演奏の質が上がったように思います。
今までふれてこなかった作曲家の曲を弾く事で様々な弾き方があることを教えて頂き勉強になっています。
一人で演奏するのと違ってパートナーがいるとあまりミスできないので、正確に弾く練習になった。アンサンブルとしてメンバーと呼吸を合わせることを学んだ。
ソロで気まぐれな練習でやってきたため、アンサンブルをやってみて、パートナーに迷惑をかけないよう、もっともっと練習をしなければいけないことを実感した。
曲の理解と取り組み方について最初のレッスンで教わったことが最も変わった点です。弾き方とか技術面より先に理解について教わるとは思ってもいなかったのでそこが最も大きな違いとなり、以降のレッスンにも明確に示されたことで自分の目標が明確になりました
Q.「音楽」について新しく学んだことは?
曲のキャラクターや自分がどう弾きたいのか、を考えたのは初めてのことで、とても新鮮で新たな発見でした。
過去にもシューマンの五重奏を演奏したことはありますが、曲に深い知識を学べたことで、シューマンならではの繊細さをより表現することが出来たかと思います。
音楽のイメージをいかにつかむか、そしてそれをどう表現するかという勉強になった。
曲の背景、歴史を知ることの大切さを目の当たりにして積極的に曲に関わる事ができました。
同じ曲でも、解釈の仕方、弾き方は、テンボを含め、十人十色であるということ。正解は無い。
フォルテ、ピアノなど強弱記号一つとっても時代によって響きが違うことを学びました。
Q.「楽譜の見方」について新しく学んだことは?
小節やフレーズの推進力を大事にする、強弱の考え方、6連符のカウント方法等、多くの新しい見方を学べましまた。
楽譜に書いている指示の意味について深く熟考する機会が増えました。今までは指示通りに演奏するだけですが、その指示に含まれる作曲者や曲の意図を読み取ることが出来るようになりました。
他のメンバーのパートも見るので、コードやメロディーの流れの変化など注意してみるようになった。
スコア譜の読み方を知る事で自分以外の楽器の音を聴く習慣づけができました。
新しくではなく、昔からの自分の課題ではあるが、スラーを最もよく見ること、フレージングを考えることが大切だと思っている。
自分のパートだけでなく他の楽器のパートと合わせて見る事で曲全体をとらえる事ができることを学びました。
Q.「他のパートに合わせる」ことについて、新しく学んだことは?
誰かと音を合わせるのは初めての経験でしたが、他の人の音を聞くこと、お互いの動きを感じること、どの部分がどの楽器が主なのかを考えること、主の楽器の音をサポートすることの重要性、出だしの合図の重要性を学べました。
誰がソロなのかを意識するところまでは出来ましたが、それを再現することが難しかったです。
具体的に「何を」と言うのではないですが、アンサンブルの経験が浅いので、この点については大いに学びになりました。
曲全体の中でどの楽器どの楽器がどの場面で主導するのか、どの楽器に寄せていくのか具体的に知ることができました。
感情移入すると、テンポルバートになりがちだが、アンサンブルの場合はテンポを一定にし、音で、歌わなければならないということ。
相手を聴く大切さを知りました。
Q. 室内楽について「まだわからないこと」「もっと知りたいこと」は?
まだわからないことだらけなので、なんでも吸収したいです。
「他のパートと合わせる」部分。
ザッツの入れ方、拍感の合わせ方、トレーニングの仕方を習いたいです。
アンサンブルにおける、フレーズごとの表現の仕方について知りたいです。誰がどの部分ソロなのか、その時伴奏の役割を果たすメンバーはどのように演奏するべきなのかといったことを学習したいです。
作曲家によって、変えなければならない弾き方をもっと知れたいし、学びたい。
まだまだわからない事ばかりですが、ふれる曲が増えていくことで知らなかったことをもっと知っていきたいです。
Q. 室内楽の「好きなところ」は?
全員の存在を身近に感じることができ、皆で音を作り上げる過程をより実感できる点です。
同じ楽器に関わらずグループになる全員が近い関係になれること。
少人数で楽しめること。
チーム力が1番試されるところだと思います。各パート1人しかいないため、一人一人の協調性に対する意識が強ければ強いほど魅力的な演奏ができるところだと思います。
仲間がいるところ。大人数のオーケストラより音楽の面でも仲間との人間関係の面でもきめ細かく深められるような気がする。
1人1人が活躍するので緊張するけど楽しい!指揮者がいないのでアイコンタクトをとったりや息を合わせて演奏するところ。テンポが変化する箇所は難しいけれど、周りを見て演奏する力がつくと思います。
すぐそばで、声をかけ合えること、メンバーが多すぎず、心を通わせることが出来る、音楽的な事もそれ以外のことも、意見交換ができること。1人ではなく、仲間と仕上げた達成感は、ソロでは、決して味わえない喜びである。
楽器一本ずつで曲を完成させるところ。メロディやハーモニーが独特で完成度が高い曲が多い事。
Q. この室内楽プログラムについて
初めての室内楽で何もわからなかったのですが、人と音を合わせるときに何に気をつけることが必要か学べたことがとても嬉しかったです。
様々な考え方に触れることが出来てとても刺激的な時間を過ごせました。
レッスン動画、あとから復習できるのでとてもありがたいです。
アンサンブルの経験が浅いものの、日本の先生のレッスンとはアプローチが違っていて勉強になりました。毎回レッスンのyou tubeをいただき発表会のフィードバックまであって、先生とSOUPの手厚いサポートに感謝です。
初めての相手と一曲仕上げるというプログラムが集中してレッスンできる要素でよかった。
先生方、共に演奏する仲間と出会えたことが良かったです。
コンサートに来て下さった観客の声だが、音響の良いホールが望ましいとのことでした。→(SOUPより)ご意見、誠にありがとうございます。熱量ある演奏を室内楽に最も適したホールで聴きたいというお気持ちは、私たちも同じです。ただ、ホール使用料に大きな差があります。SOUPでは参加しやすさ、継続しやすさも大切だと考えています。世界的に活躍する講師陣にご指導いただきながら、月1万円強の授業料を維持できるのは、良心的な渋谷ホールさんのお力も大きいです。さらに、丁寧にメンテナンスされたファツィオリのピアノの美しい響きもお楽しみいただけます。
受講生が増えたら、発表会だけでもエントリーシステムはやめて良いのではないでしょうか。受講生があの場で聴きたいのは、同じようにレッスンを受けて仕上げてきた演奏だと思いますので。
→(SOUPより)
ご意見、誠にありがとうございます。リサイタルでの外部団体様の参加は、発表の場を探している室内楽ファンのために設けました。楽しみにしている方もおられますので、順番などを工夫いたします。
自分は奏者募集の情報を見つけてから申し込みをするまでだいぶ悩みました。自分のレベルでも参加していいのか、初級・中級など書いてあるけど実際どれくらいなのか、オンラインレッスンはどのような感じなのか、初対面の人たちとうまくやっていけるのか等…。室内楽は一人ひとりが目立つのでオーケストラに参加するよりもハードルが高い感じがします。 ホームページのレッスン風景の動画は参考になりました。レッスンや本番の動画・写真などがもっと見れるとイメージしやすいなと思います。
スタッフが、ご多忙にも関わらず、一人一人に寄り添ってくださり、親身になって考えてくださること。
SOUPの会のおかげで、素晴らしい先生方から多くの学びを得ることができました。本当にありがとうございました。
先日の演奏会ではお世話になりました。秋学期も引き続きよろしくお願いいたします。
SOUPスタッフより
このフィードバックは、スタッフに大きな喜びをもたらしてくれました。
約半年間にわたる室内楽プログラムの完遂には、時に苦労があります。特に、忙しい講師陣と、それに負けず劣らず多忙な奏者の皆さんとの日程調整は、毎回頭を悩ませる作業です。
それでも、学期中の皆さんの音楽と向き合う真摯な姿、そして最後にこれほど多くの貴重なご意見を寄せてくださったことに、大いに励まされました。講師の先生方、参加者の皆様、本当にありがとうございました。